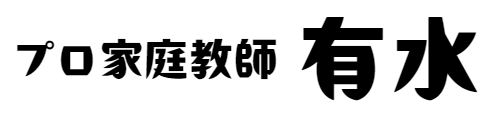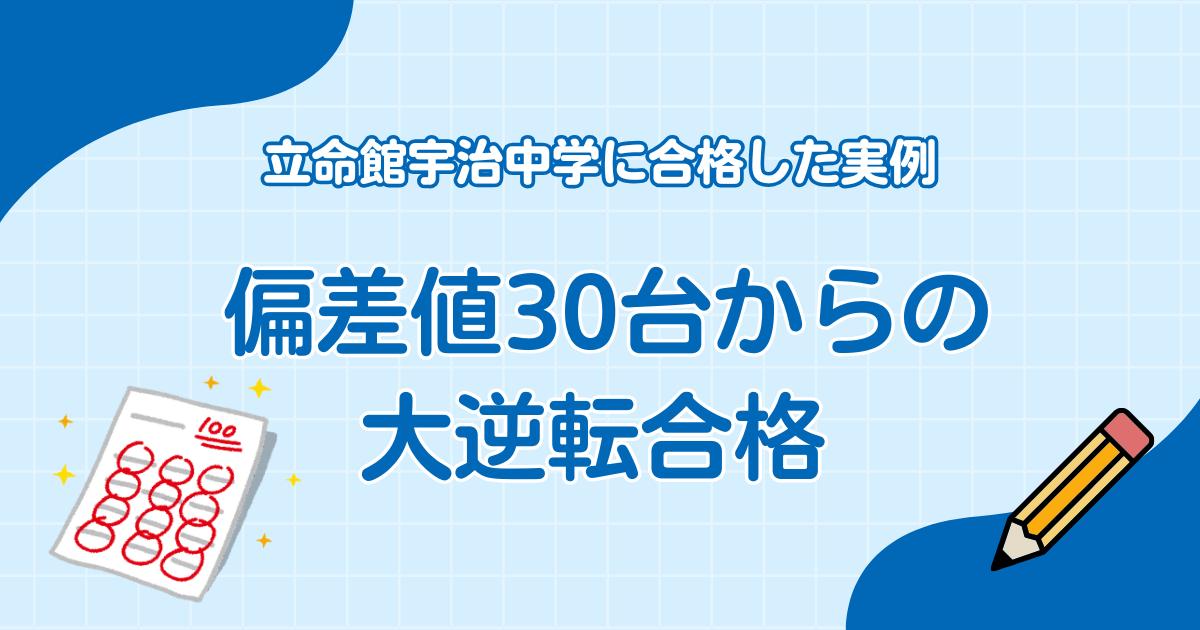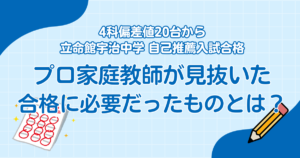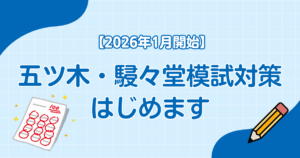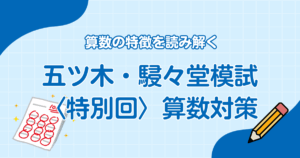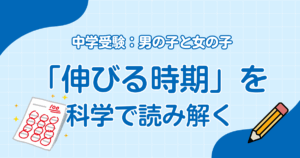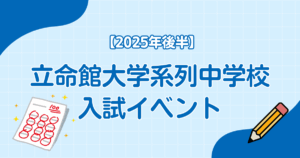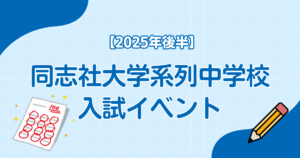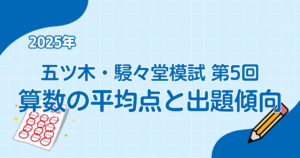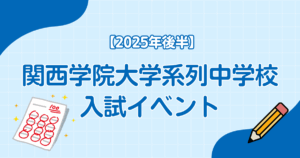学年:小学6年生(指導開始時点)
この生徒のお姉さんを以前に指導していたのですが、ご家庭から再びご依頼いただきました。お姉さんのときも非常に良い関係を築くことができたため、弟さんの指導も信頼して任せていただいた形です。
指導開始時期:6月中旬
目標:立命館宇治中学 合格
状況:小4から塾に通っていたが、成績はずっと低空飛行。授業中は居眠りや離席もあり、家庭でも集中力が続かず、お母さんからは不安の声が多く寄せられていた。
塾で話を聞けない子が、家庭教師で驚きの集中力を発揮!
塾で成績が上がらない子の実態とご家庭の不安
塾では「ふにゃふにゃしていて、先生の話を聞けているのかもわからない」とのお話。 家庭でも何を考えているのか分からず、受験に向けて本気なのかどうかすら見えてこない、とのことでした。
お母さんとしても、どうしたらいいのかわからないといったご様子。 家庭教師でも変わらないのなら、受験自体をあきらめるとのことでした。
勉強面では偏差値が30台で、志望する関関同立の付属校はまったく手が届かないレベルでした。
■ 初回指導で大きく変化
初回指導の前、わたし自身も多少の覚悟はしていました。「もしかしたら机に向かうことすら難しいかもしれない」と思っていたのです。しかし、そんな不安は良い意味で裏切られることになります。
初回の指導から、意外にも非常にハキハキと集中して取り組んでくれました。 ナチュラルな姿勢で90分間こちらの指示通りに行動し、雑談もなく真剣そのもの。 わからない問題に対しても、あきらめることなく粘り強く取り組む様子が印象的でした。
こうした集中力の高さに、お母さんも「信じられない」と驚いておられました。
多人数のなかでは、意識がどうしても散漫になり、集中できないタイプの子がいますが、この生徒もきっとそうだったのでしょう。 家庭教師がばっちりはまりました。
家庭教師の成果、成績の変化
こうした変化は、ただ単にテストの点数が上がったというだけでなく、本人の「自信」に直結していきました。1問答えられた、という事実が「自分にもできる」という感覚を芽生えさせたのだと思います。
指導から1か月が経った頃、塾の授業中に先生に当てられて、やや難しめの問題に正解したそうです。
「○○くんが答えた…」
そんな感じで教室がざわついたとのこと。 そして、このことに関して、先生からご家庭にわざわざ連絡があったそうです。1問答えただけなのに、それくらい珍しいことだったのでしょう。
それ以降、週末の復習テストの点数がみるみる上昇。 塾の先生からは「覚醒したな!」という言葉も。
さらに、
- 指導から5か月後、日能研の公開模試で偏差値53を記録(算数)
- 塾内テストで算数100点を獲得
- 過去問では関関同立付属校の合格最低点を大きく超える点数
塾からも「付属校も十分勝負できる」と太鼓判を押されるまでに成長しました。
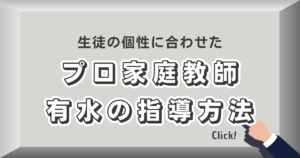
メンタルの成長、そして…
入試直前の悲劇
入試まであと1週間を切ったある日、お母さんが急な体調不良で緊急入院することになりました。 子どもにとって、それも男の子にとってお母さんはなんといっても精神的な支柱。
「だいじょうぶ…か…?」 彼の精神的なショックを、わたしは心配しました。
「はい!お母さんに心配かけないように、勉強頑張ります!」
本人はいたって動揺することなく勉強に集中。 精神面の大きな成長も感じさせてくれました。
合格
入試当日は、やや緊張した様子ではありましたが、これまでの努力の積み重ねを信じて落ち着いて試験に臨めたようです。特に算数では、最後の最後まで見直しをしてケアレスミスを防ぐなど、以前の彼では考えられなかったような姿勢で取り組めたそうです。
そして最終的に、第一志望だった関関同立の付属校に合格。 6月に依頼をいただいた時点では、偏差値や学習状況を見ても到底届かないと感じられていた志望校でしたが、わずか半年ほどでしっかりと合格を勝ち取りました。
この結果は、本人の努力の成果です。 そこに、環境や接し方を変えることで「できるようになる実感」を持たせたこと、そしてそれを積み重ねられたことも重要な転機だったのではと思います。
家庭教師として感じたこと
中学受験は、学力だけでなく、精神面の成熟度や日々の生活習慣までが問われる厳しい挑戦です。成績が振るわないときにこそ、適切なサポートと関わりがどれほど重要かを、あらためて感じさせられたケースでした。
この子のように、塾では力を発揮できず「できない子」と見なされているケースでも、接し方と環境が合えば、急激な成長を見せることがあります。
わたしは、塾や集団指導では力を出せない子にこそ、家庭教師という選択肢が有効だと考えています。
このようなケースに心当たりのある方は、ぜひ一度ご相談ください。
※この記事で紹介した指導の背景や考え方については、以下の記事でも詳しく書いています。 また、成績不振の生徒には小さくてもいいので目先の結果を出すことが大事だと考えています。 この生徒の場合は、頻繁に行われる小テストで高得点を狙いにいきました。 ただし、どのように勉強させるかは、その生徒の特性によって変える必要があります。
▶「プロ家庭教師有水の指導法-『型』を持たない理由ー」