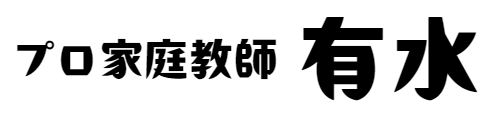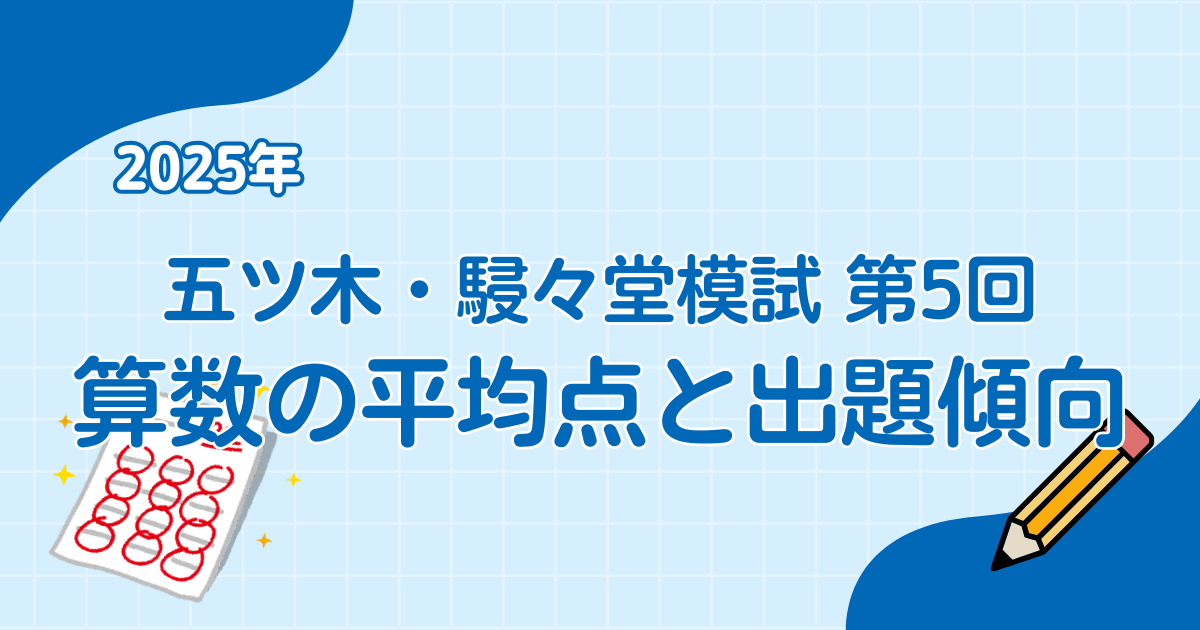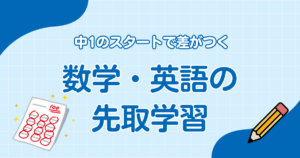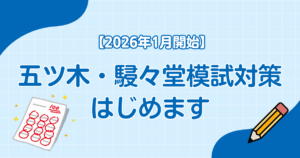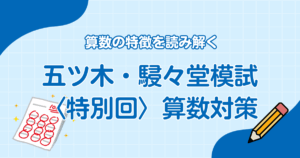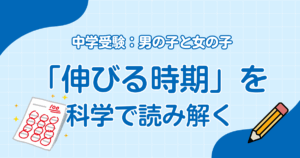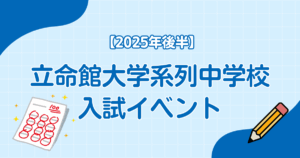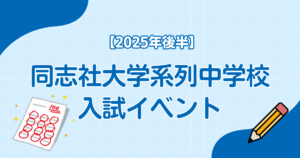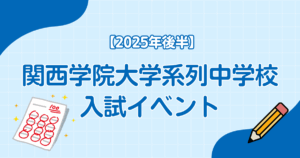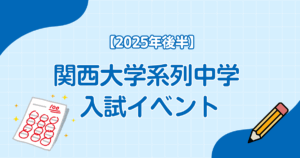五ツ木・駸々堂模試の第5回は、9月末実施。夏休みの取り組みがどれだけ“定着”しているかを測る重要回です。ここでの結果をもとに、秋以降の学習方針(弱点補強/志望校調整)を具体化していくのがポイントです。算数は年度ごとの難易度の波が大きい科目ですが、過去の傾向を整理すると出題の特徴が見えてきます。
目次
五ツ木・駸々堂模試第5回の平均点と標準偏差
| 第5回 | ||
|---|---|---|
| 年度 | 平均点 | 標準偏差 |
| 2019 | 36.0 | 21.7 |
| 2020 | 41.7 | 20.6 |
| 2021 | 43.5 | 21.6 |
| 2022 | 43.9 | 19.6 |
| 2023 | 38.5 | 20.4 |
| 2024 | 50.0 | ― |
平均点の推移
- 2019年:36.0点 → かなり低め(難化した年)
- 2020~2022年:41~44点台 → 安定して40点台前半
- 2023年:38.5点 → やや難化
- 2024年:50.0点 → 直近で最高値、大幅な易化
直近6年間で 平均点は36点~50点の間を上下 しており、年度による難易度のブレが大きいことが分かります。
標準偏差から見えること
- 標準偏差は 約20点前後で安定。
- これは「点数の散らばり方はほぼ毎年同じ」であることを意味します。
- したがって「平均点が上がっても下がっても、得点分布の幅は一定」。
→ 難易度の上下がそのまま平均点の上下につながっている。
五ツ木・駸々堂模試第5回 年度別の出題傾向(概要)
- 2019年:図形でひねりのある問題(正方形+円・面積比)が登場。規則性も複雑で平均36点。
- 2020年:速さや食塩水は標準的、立体図形は計算処理力が問われた。
- 2021年:計算問題が多くスピード勝負。食塩水は基本形。
- 2022年:全体的にバランスが良く、40点台前半で安定。
- 2023年:小問集合に工夫が必要な整数問題が並び、図形もやや複雑。平均は38.5点まで低下。
- 2024年:典型的な食塩水・速さ・損益算、図形も折り返しや回転など標準レベル。大幅に得点しやすく平均50点。
五ツ木・駸々堂模試第5回2024年度の特徴
- 計算問題:標準的な四則混合。工夫を要する計算は少なく、得点源になった。
- 小問集合:整数の性質や割合など、基本を押さえれば対応可能。
- 図形:折り返しや回転移動など典型題。条件処理が複雑な問題はなく、落としにくい。
- 文章題:速さ・食塩水・損益算といった“受験生が必ず練習している題材”。奇問はなし。
→ 基礎+標準題を取り切れるかどうかが勝負の内容で、例年に比べて得点が伸びやすかった。
傾向から見える学習ポイント
- 年度ごとの差が大きい
- 難化した2019年・2023年では平均点が30点台後半。
- 2024年は一転して50点に上昇。
- → 点数より「偏差値」で実力を把握することが重要。
- 頻出分野は不動
- 食塩水・速さ・規則性・図形(折り返し・回転・展開図)は毎年の定番。
- どの年度でも得点源になるので、重点的な練習が必須。
- 基礎計算が勝敗を分ける
- 難しい年でも必ず計算や小問で取れる部分はある。
- 平均点が下がる年ほど「落とさない力」の差が大きくなる。
まとめ
- 2024年第5回の算数は、直近6年で最も得点しやすい回(平均50点)。
- 典型問題中心で、基礎と標準問題をしっかり解けば得点が伸びた。
- ただし2019年・2023年のように難化する年もあるため、過去問演習では「易しい回」「難しい回」の両方を経験しておくことが大切。
- 2025年第4回が難化したように、結局のところは難易度の予測は不可能に近い。
第5回で結果を出すには、基礎を徹底しつつ頻出分野の典型題を確実に押さえること。難易度の波に左右されない「安定した得点力」を養うことが、合格への近道となります。